支配されない私でいるために。ちゃんと揉めて、ちゃんと治める話し合い
土山 希美枝(つちやま きみえ)
法政大学法学部教授
1971年北海道芦別市生まれ。2000年法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻博士課程修了。博士(政治学)。2001年龍谷大学法学部助教授として着任。職名変更により2007年より准教授。2011年4月、学部新設にともない政策学部に移籍、2015年4月、政策学部教授、2021年から法政大学法学部教授。専門は公共政策論、地方自治、政治学。主な著書に『高度成長期「都市政策」の政治過程』(日本評論社、2007)、ほか、共著『対話と議論で〈つなぎ・ひきだす〉ファシリテート能力ハンドブック』(公人の友社、2011)、『「質問力」からはじめる自治体議会改革』(公人の友社、2012)、近刊に、『「質問力」でつくる政策議会』(公人の友社、2017年8月)、共著『公共政策学』(2018、ミネルヴァ書房)、『質問力で高める議員力・議会力』(中央文化社、2019年2月)などがある。2019年から『議員NAVI』(第一法規ウェブマガジン)にて「ヒロバな議会でいこう」連載中。
地域課題解決のための「つなぎ・ひきだす力」
今日は公共政策学を専門とされている土山さんが、「話し合い」をどのように捉えていらっしゃるか伺えたらと思っています。まず最初に簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
土山 私は北海道の芦別市という旧産炭地の町の出身です。エネルギー転換で石炭が石油に変わる頃からどんどん人口が減っていった町で、最盛期には8万人近くいた人口が今では1万3000人を切ってしまっています。子供の頃は、人が死ぬから町の人口は減っていくのだなと思っていたのですが、どうやらそういうわけではなく、人口が増えている所もあると知りました。私の地元は、好きだからといってずっと住んでいくのが難しい町でした。それはどうしてなのだろうと疑問に思ったのが、この分野に進んだきっかけです。まだ子どもだったので、そういうことを学ぶには政治か経済を学んだらいいらしいと考えたんです。
その頃はまだ、政策学という学問領域は確立していませんでした。今でも政策学は、学際的=学問の際だと言われています。そんなこともあって、最初は政治学の中の公共政策の道に進んだんですが、そこで受講した松下圭一先生の授業にすごく心を揺さぶられたのです。それがまさに今でいうところの政策学でした。当時は「政治」というと、保守か革新か、与党か野党かというような話が多かったのですが、松下先生のお話はすごく面白くて、自分たちが自主的に、自立的に学びを深めていくような時間でした。当時その発想は、割と異端だったのですが、とにかく私はすごく共鳴して、大学院に進学したんです。その後いろいろなご縁があって、今は研究者として地域政策や地方自治の面から持続可能な地域について研究をしています。
ーーちょうど日本で政策学という学問が広がり始めた頃に、研究者としてのキャリアをスタートされたのですね。分野を横断する学際的な学問ということは、今日の取材テーマである「話し合い」とも関わりが深いテーマだといえそうです。
土山 そうですね。2003年に大学内の研究グループが始ったのですが、ひょんなことから、そこの人材育成に関わるプロジェクトチームを代表することになりました。そこで地域政策を担う人材に必要な力を考えると、コーディネート能力、ディレクター的な能力、リーダーシップ、マネジメント力など、いろいろなものが挙がってきました。その全部を合わせたら、それはもうスーパーマンでしかありえないわけです。そこで少し発想を変えて、地域政策を担う全ての人に必要な力は何かを考えることにしました。
日本は他の国と比べて、セクター間の分断が激しいという特徴があります。例えばイギリスやアイルランドなどでは、自治体職員もヘッドハンティングでの異動があったりします。日本の雇用市場と違っていろんな所を行き来するので、人材の交流が活発なんです。日本の場合は同業の中ですら分断が激しいので、同じ業態でも全く文化が違ったりしますよね。それは、キャリアの最初から最後までずっと同じ会社にいることが良いとされる日本型雇用のもたらしている影響です。そうすると、その分野の価値観に染まることが当たり前になってしまい、業界や分野を越えた関係性をつくることが難しくなります。当時は社会課題の解決のために、NPOと自治体の協働が大切だといわれながらも、お互いが個性を理解しあえていなかったんです。その結果、企業は「あいつらは儲け優先だ」と言われ、NPOは「趣味でやっているだけだ」と言われ、自治体は「税金でズルばかりしている」と言われる、そういう世界になっていたわけです。
地域にある課題というのは、分断を越えて地域のみんなに共有される政策課題なわけですよね。お互いの違いを超えて一緒に活動したり、競争したり、少なくとも課題を課題だと認識しないと、課題解決には至らないのです。そのために何が必要なのかというと、お互いの違いを超えて課題を共有し、その課題に対して何かを成す力です。そして、そのためにはセクターを越えた対話や議論が重要です。対話と議論を通じて課題を共有し、その結果として理解や共感を生むような「つなぎ・ひきだす力」が大切なのではないかと考えています。
ーー社会の問題解決にとりくむためには、分野や領域を超えた連携が大切で、そのためのつながりは話し合いから始まる、と。冒頭でおっしゃっていた日本の地方が抱えている多くの課題も、1つの主体でどうにかするのは難しそうな問題です。
土山 理解というのは、「この人とは分かり合えない」ということでもいいんです。ひょっとしたら10年後に何かが始まるかもしれないし、私と相手の間には何も起こらなくても、別の新しい人との出会いにつながったりするかもしれません。一度関係性が生まれると、それ以降なにかを一緒にするのが楽になりますよね。だからこそ、話し合いを通してセクターを越えてつながりやすく、ひきだしやすい社会をつくることが理想なんです。
ただ、それは音声による対話からのみ生まれるわけではありません。私は1人の先生の授業に出会って人生が変わったわけですが、文字や映像のメッセージに感動するということもありますよね。理解や共感を引き出すための媒体は音声に限らないということです。そういう理論や方法をどうすれば実りあるものにできるか考えるようになったのが、「話し合い」との出会いだといえます。

土山 私は生まれてからずっと変な人というキャラなのです。ずっと変わっていて、ずっとおかしな人なんです。。
ーーなるほど。周りからそう言われることが多かったのですか。
土山 周りからも言われるし、自分でもそうだと感じています。自分の興味を持つものを、周りがあまり興味を持つわけではないのだなと感じる場面が多かったように思います。自分はここにいることが許されるのかという思いが常にありました。中2病という言葉が、私にはすごく心に刺さるんです。私は間違いなくそうでしたから。というか、今でも卒業できてないかもしれません。(笑)私はおっちょこちょいでうっかりで、人として本当に駄目なのです。。
ーー思い返してみると、思春期は周りとの個性の違いや、自分とはなにかという悩みがあった気がします。
土山 私の一番古い記憶は、幼稚園に行く角を曲がる時に、大人が私のことを「子ども」と思って見ているという場面です。その時の私は、「大人が思っているほど子どもじゃないのよ」という思いと、「でも本当は子どもなんだから仕方ない」という思いを同時に感じていたんです。自分は何者なのかを、子どもながらにすごく考えていたように思います。私が少数者だったからかもしれませんが、自分が周りからどう見えているか、自分の心が何を好きかをすごく意識していました。基本的に少数者は迫害される恐れがありますよね。だからこそ、世の中がもっと疎外されない社会になればいいなと思っているんです。
ーーなるほど。
土山 「何だかんだいっても希美枝ちゃんも結婚するよね」と言われたことがあるのですが、私は結婚しないなどと一言も言ったことがないのです。自分の未来を拘束することを言うのは嫌だったからです。なぜかというと、そうではなくなった将来が嫌だからです。あと、小学校の頃に作文で「大人になったら何になる?」というのテーマがありましたよね?いつもあれをどうごまかそうかと思っていました。(笑)大人が期待しているとおりに振る舞うのが嫌でした。それでも、周りや兄弟と比べて、どうして自分はこうなのだろうというような気持ちもあるわけです。基本的に自己肯定感が低いけれども、自己意識が高かったんでしょうね。理想の自分像がありつつ、いわゆる大人が期待する子ども像は嫌だという。そういう意味では、支配されないでいることへの渇望があったんですよね。
ーーそう考えると、支配に抗う少数者に寄り添った理論でもある政策学を志されたのは、土山さん自身の問題意識ともつながっていたのかもしれませんね。
土山 私が大学のときに受けた松下圭一先生の授業に「都市型社会」という言葉が出てくるのですが、それは、人々が互いに自由でありながら、さまざまなシステムや制度によって支えられている社会を指します。そこでは私たちは自由でいていいのですが、自由同士は衝突するわけです。そうなると、衝突したときにどうするのかを考えるのが重要になります。
衝突したときには、何かルールをつくるわけですが、それは誰かが勝手に決めるわけではなくて、両者の合意で決めるべきことですよね。その社会がだんだんと大きくなると、全員の合意を調整するのが難しいので、別のシステムが必要になってきます。それが本来は政府の役割なわけです。つまり、今の社会は誰も支配されない社会のはずなんです。でも、実態としてそうなってはいません。授業を見ていても、私たちは支配されることにすごく慣れてしまっているのです。例えば、「空気を読め」という考えです。そういう社会の中で話し合いに求められるのは、自分の思いを自由に表現することです。「自分がこう思う」という意見をもった支配されない私同士だからこそ、つなぎ・ひきだすことが可能になるんです。
ーーなるほど。
土山 話し合いは、対話の作法に限らず、「自分とは何者か」という問いが重要です。大学での学びがもっと職業的な役に立つようにすべきだという意見がありますが、私がその話に違和感を持つ理由は、自分とは何者かということに向かい合える学びの期間が大学生活ではないかと思うからなんですね。自由で平等な個人として話し合える環境は、大学の大きな価値だと思うのです。
残念ながら、日本の高校は支配することによって成り立っています。高校生までは、子どもは大人の言うことを聞くものだという支配的な教育を受けるので、自分とは何者かという問いや、自分の政治志向などを磨く間がありません。そんな状況でいざ選挙を迎えても、突然自分なりの選択などできるわけがないなと思うのです。
ーーまだ自分の意思で選択をした経験が少ない状況ですからね。
土山 選択する権限があるということは、自分と、自分の集合体である自分たちで決めるということです。自分たちで自分たちのことを治めるというのが自治ですよね。「自治」というのは面白い言葉で、「みずから治める」と皆さんは捉えていらっしゃると思いますが、昔の文書では「おのずから治まる」という意味を表すことがあるのです。おのずから治まるというのは、放っておいても悪さをしないということです。放っておくのは誰かというと、権力を持っている人です。放っておいても自分にちゃんと従っているというのが「おのずから治まる」なのです。
日本の教育プロセスは、おのずから治まることを期待される期間が長く、自分たちで治めるという経験がないので、いろんなものが形骸化してしまうのです。例えば、中学校で生徒会に自由な予算を30万つければ、予算を巡ってけんかをしたり、リコールがあったり、権力闘争などが起きるかもしれません。それは学びになるはずなのですが、そんな経験はあまりできません。私たちには、空気を読んでみんなでほわんと決めるというよりも、自分たちで治めるという経験が必要なんです。そして、治める前には、揉めるという段階がある。「ちゃんと揉めて、ちゃんと治める」ことが大切なのです。
ーー話し合いは、ちゃんと揉めてちゃんと治める技術の1つなんですね。
土山 いわゆる対話というのは、友好的な関係をつくるための話し合いという意味に受け取られがちですが、対話と議論をセットにして考えないといけません。それが、ちゃんと揉めて、ちゃんと治めるということなのです。そのベースになるのは自分自身の考えなので、まずは自分とは何かということを考えないといけません。
ーーそういわれてみると、小さい頃は喧嘩を通して多くのことを学んだ気がします。他人とのあいだで起きる摩擦を通して、誰かの痛みや自分のこだわりに気づくことはありますよね。
土山 社会のあらゆる改革は、少数派からの問題提起から始まるということです。政策や制度のネットワークは大体組み上がってしまっているので、「ここがおかしい!」という指摘がないと世の中は変わりません。みんなが気づいていれば、すでに変化が起きているはずですから、声を挙げるのは少数者などの弱い立場の人になるのです。その問題提起が社会として対応すべきものなのかは別の問題ですが、少数者からの問題提起が社会の中で争点として認められやすい社会というのは、政策や制度のネットワークがブラッシュアップされやすい社会なのです。対して、変えられない社会はそこに至るまでの間に苦しむ人がいっぱい出るのですからコストの高い社会といえます。
ーーなるほど。
土山 ちゃんと揉めて、ちゃんと治められる社会であったほうがいいですよね。でも今は、揉めることがあまり良くないことだという考えがあるでようです。学生とやりとりをしていると、デモが悪いことだと言うのです。
ーーそれはどういう理由なんでしょうか。
土山 暴力に至ることがあるからです。もちろんエキサイトして暴力につながる問題は考えなければいけないけれど、コントロールしきれないこともあるわけです。コントロールできないことをやっては駄目だと言うなら、毎年3000人も死者を出している自動車はなぜ許容されるのでしょう。社会にとって必要な機能であれば、それをより良くコントロールすることに注意を払うべきです。つまり、どうやったらデモが暴力的にならないかということを考える必要はあるけれども、暴力的になる場合があったり、周りの迷惑になるからデモはやめろ、という考えには待ったと言いたいのです。社会はデモ行進や集会などの少数者の問題提起をあまりよしとしないですよね。それは学校教育も同じで、みんなが同じものを受け入れることが求められてしまいます。管理する側はその方が楽なんですよ。
ーーなるほど。学生さんにとっては公共の場で怒りを表明することに抵抗感があるのかもしれませんね。
土山 違法だから駄目だと言うのであれば、バイト先の雇用状況は本当に問題ないのでしょうか。一緒に労基に行こうよと言いたくなりますよね。
ーー確かに。急にバイトを休まなければいけなくなっても、代わりのシフトを探す必要なんてないですからね。(笑)
土山 そうです。これは支配されることに慣れているから起こる問題です。デモは嫌だというのは、おのずから治まっているほうが美しいという考えがあるからでしょう。おかしいことに対して自分の意見が言えないのです。

対話と議論による問題提起
土山 法律などの自由の衝突を避けるためのルールの下では、自分の自由が制約されても支配とはいいません。例えば、友達とワイワイしゃべっている人に、「あなたは私の授業の邪魔をして他の人の邪魔になっているので出ていってください」というのはありでしょうか、なしでしょうか。
ーーありだと思います。
土山 ありですよね。では、「あなたのことが気に入らないから出ていってください」と言うのはどうでしょう?
ーーなし、でしょうか。。
土山 そうですよね。どちらも教室を出ていくように言っているのに、何が違うのでしょうか。それは、その教室が学ぶために良い空間であるようにコントロールする権限を私が預かっているからです。私とその学生の間にはシラバスという契約があって、教室はそのシラバスに書いてあることを達成するための場なんです。私は自分が持っている知見を提供するし、それを学生が受け入れることができるように、その場をより良い環境に保つ義務と権限を持っています。ただ、追い出すときには、学生の学ぶ権利も侵害するわけですから、「私は学びたいです。もう邪魔はしないので教室にいます」と言われた場合は、別の判断に変わるでしょう。気に入らないから出ていきなさいというのは、全くその権限と関係ありませんよね。権限の範囲を越えて他人に何かをさせようとする力、権限を越えた権力の行使こそが支配なのです。
ーーなるほど。
土山 支配の構造が色濃く残っている社会を次の世代に渡していることに、私は責任を感じています。だから、授業ではとにかく「ちゃん揉めなさい」と言います。私は支配されたくないし、学生を支配したくもないからです。
ーー自由でいたいのならば、私たちは揉めることを手放してはいけない。
土山 不倫や不祥事があった際に「お騒がせしました」「不快にさせてすみません」という謝罪の仕方がありますが、あれは社会の中で共有されるべき価値観の衝突を回避しているわけです。それでは何が悪かったのかが分かりませんよね。
ーーすぐに炎上してしまうSNS環境が、世間の謝らなくてはいけないという空気感を増長させているようにも思います。
土山 SNS上で起こっているようなバッシングは、他人の自由を簡単に侵害するのですよね。支配される/支配することに自覚がないから、悪いやつには何をしてもいいと勘違いして不当な権力を行使してしまうわけです。
ーー昨今のインターネットポピュリズムの加速は、支配される/するということに無自覚である私たち自身にも原因があるんですね。
土山 意識されない支配が世の中に蔓延しているんです。ましてや新型コロナの影響は、他者と自分との関係を敵対関係にしがちです。他人がウイルスを持っているかもしれないと考えると、全員が敵になってしまうのです。だから、マスクをしない人に対してものすごく厳しいでしょう。それは自分に対する敵対行為なのであって、自分の安全がひどく脅かされる状況だからなんですよ。
ーーたしかに世の中の規範にあわせなければいけないという同調圧力を感じる機会は多いかもしれません。多数派の論調に乗っていれば自分で思考せずとも正しいことを言っているような気になれてしまう。
土山 規範を受け入れて我慢していたら、支配される代わりに守ってもらえるかもしれない。支配されることの安楽があるのですよ。自由というのは、自分で決めることができるということですが、全部を決めないといけないというのは結構大変です。例えば、私は買い物が大嫌いなんです。デパートへ行って、あんなにたくさんの物の中から1つを選ばないといけないというのがシンプルに苦行なので。(笑)もちろん自分が好きなものだったら選ぶ喜びはありますが、何もこだわりがないのに選ぶというのはつらい。自由は時としてつらいのです。
ーーSNSには声の大きい人の発言がそのままコピーされて溢れかえっています。多数派の意見に同調することの安楽が、人を考えなくさせてしまっているといえるかもしれませんね。政治的な正しさを主張する運動なんかがそうですが、シングルイシューで簡単に連帯してしまうと丁寧な議論が生まれづらい。問題が誰のどんな自由を侵害しているのか、自分たちの問題設定が間違っていないかという考え抜きに、条件反射的に反応してしまっているように思います。
土山 エキサイトして、誰かをさらすことが気持ちよくなるわけですね。
ーーそういった連帯のあり方に対しては、私は少し懐疑的なんです。デモ運動や署名活動などは社会課題に対する働きかけとして非常に重要だと思う一方で、そこに思考停止で参加したり、ある政治的主張に自分を重ねてポジショントークをする人もいる。大きなイデオロギーが喪失した今、社会問題に関わることは自分たちの自由の獲得への第一歩ですが、それは本当に自分に向き合った上での叫びなのか、私とは何かという問いを経由した上での行動なのかを考え直すべきだと思っています。思考せずにマジョリティに溶け込む快楽に浸っていては、支配の構造からずっと抜け出せない。
土山 人とつながったり市民活動を起こすことは、基本的にシングルイシューです。私は他者の意見や批判を引き受ける限りは、シングルイシューでつながること自体はいいと思っています。おっしゃられているように、思考停止してしまうことが問題なのです。先ほど、大きなイデオロギーがなくなったとおっしゃいましたが、「強い人には逆らうな」というのが現在の大きなイデオロギーだと思っています。強い人に逆らわないという空気のもとでは、問題提起が生まれません。問題提起をしない政治的中立というのは、多数派の勝利につながってしまうんです。
ーー黙っていることは、多数派へ加担することになってしまうわけですね。現状を変えるには、問題提起を起点に多数派に対抗する仲間を巻き込んでいかなければいけない。ただ、数をうまく集めようというだけの戦い方には問題があるようにも思います。選挙だけでなくインターネット上での世論形成もそうですが、リツイートやいいねの数が指標になってしまうと、質ではなく、いかに数を集められるかという点にだけ意識が注がれてしまう。署名が何件集まったか、デモや集会に何人集まったかというのも大切ですが、数の論理に飲まれすぎないように問題提起の質を高めていく視点も大切だと感じます。
土山 何だか数を獲得するというのが悪いことのように聞こえるのですが。
ーー数を獲得することはもちろん必要です。しかし、ポピュリズム的に一時の人気を獲得する戦略をとるということは、長期的に見ると数の戦いに自分たちから踏み込むということになります。それは結局、次にまた上手に数を集める人たちが勝ってしまうのではないかと思うのです。そういったパフォーマティブな戦い方は、ある意味で人々の思考停止を促してしまうのではないかと思うんですが。
土山 それはすごくよく分かります。難しい問題ですよね。
ーー目的を達成するためにコスパのいい方法でとりあえず数を集めよう、という話になってしまうと、思考停止の人たちを巻き込んだほうが早いという結論になってしまいます。例えば社会問題に対する署名活動は簡単に関わることができますが、本当に自分の頭で問題について考えているのかというと、そうとは言えないケースも多いのではないでしょうか。これは責任をもって自身の意見を表明しているとは言えないように思うんですね。つまり、勝ち負けを決める場所と、人が自分と向き合って考える場所には少しズレがあるのではないかと感じるんです。
土山 少数派が自分たちの問題意識に共感する人を増やすには、困っている当事者と、それを放っておけない仲間を拡大していくしかありません。認知が広まると、当事者と一緒に署名運動をする人や、当事者と一緒にデモしようという人、寄付する人、心の中で応援しているよという人、リツイートで協力する人など、支援者のバリエーションが増えていきます。当事者と支援者が広がらないと、社会の中で課題として認知されないのです。積極的な支援者を獲得しつつ、社会の中で認知を拡げていく方法については、社会課題に取り組む人みんなが真剣に考えなければいけない問題です。そして、そのときに対話と議論が必要になるのではないかと思います。
ーー同感です。人間はコミニケーションの様式やプラットフォームの力学によって動かされてしまいます。だからこそ、問題提起を通して認知を広めていくことと、人々の思考を深めていくこと、それぞれに適した技術や場所を考えることが大切な気がしています。
土山 技術というのは可能性です。良く使われることもあれば、悪く使われることもあるわけです。今後はネットリテラシーを学校でも教わるようになるかもしれません。フェイクニュースをリツイートしたら知性を疑われるということが常識になると思いますよ。
ーー技術と評価基準をセットでアップデートしていく必要があるわけですね。
土山 例えば活字での議論は、最終的には揚げ足取りになってしまいます。それぞれのメディアの特性を理解しながら話し合うことが大切ですね。
我と汝から「私たち」へ ー 揉めることに敬意を払う
土山 19世紀にマルティン・ブーバーという神学者が書いた『我と汝』という本があります。その本では、人が外の世界を認識するには、「it(それ)」と、「you(汝)」という2種類があるとされています。例えば咲いている一輪の花をみて、心が動かされることがありますね。これは、世界に存在する対象物と自分との関係が、「我」と「汝」の関係だということです。私は花を摘むことができるし、花を摘まないで、そのまま香りをかぐこともできます。その姿や香りによって、自分の心の中の何かが動かされて、以前とは違う自分になる可能性があります。
しかし、花を単なる「それ」と捉えると、踏みつぶしても心が痛みません。その場合の対象物は、自分にとっていかに利益になるかということが価値になってしまいます。
美しい花をみて、自分と世界をつなげる人もいれば、その対象が滅ぼうが特に何も感じない人もいるということです。そういう意味では、よい話し合いは「我」と「汝」の間に起こります。私と相手の両方にとって、何かが変わり得るという前提が話し合いにはあるのだと思います。
ーーなるほど。話し合いは「汝」と相対する可能性が高いコミュニケーション方法なんですね。今のお話は、よい話し合いとはなにかを考えるヒントのように思います。
土山 相手と自分は違う人間だということを前提にしつつ、互いにつなぎ・ひきだしあう。そんな話し合いを通して、「我」と「汝」の関係、つまり私とあなたの関係を、「私たち」の関係にできればいいなと思っています。
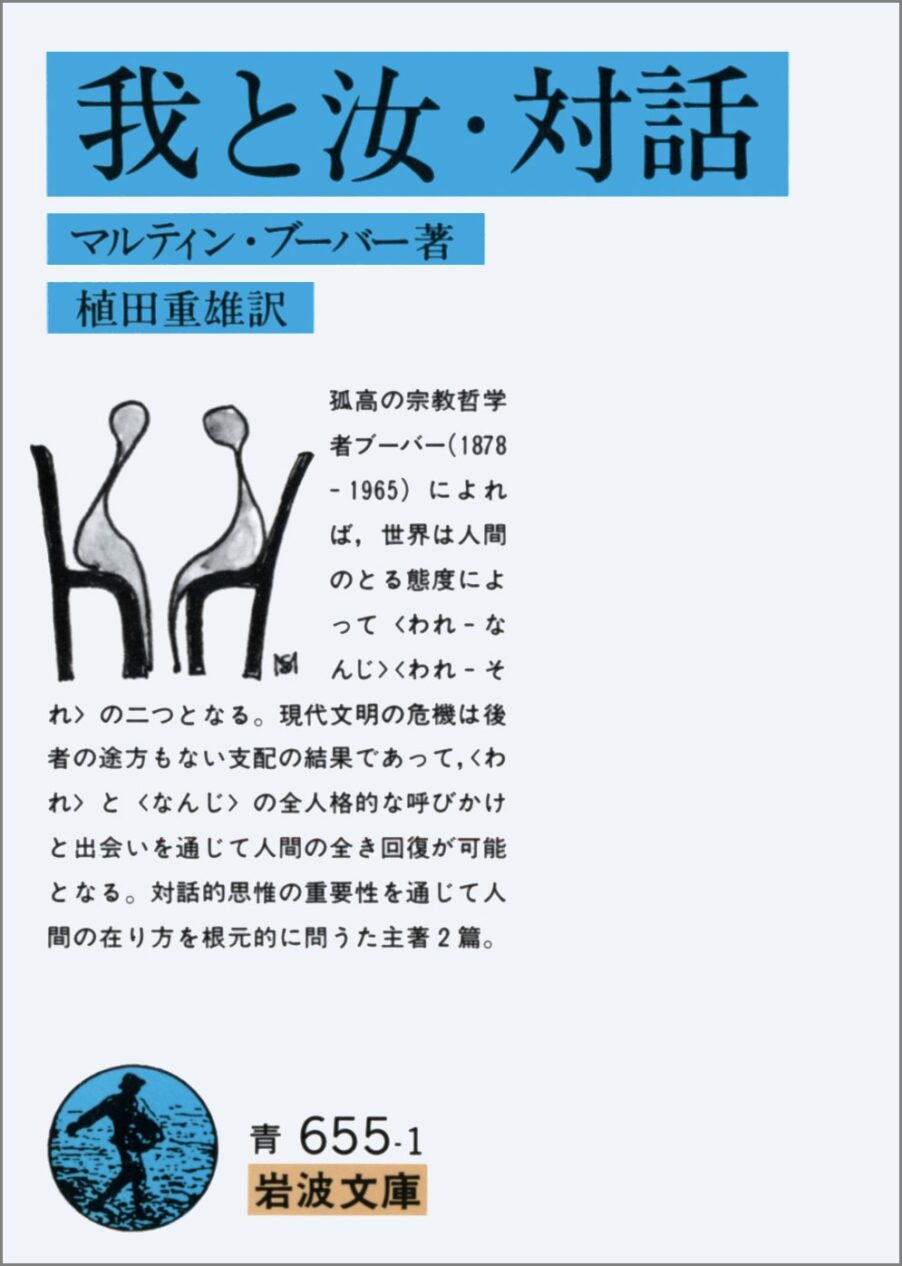
ーー署名やデモというのは、社会問題に対する間接的な関わり方なので、「汝」に対する想像力が比較的生まれづらい。けれど、話し合いのつなぎ・ひきだしあうプロセスは「それ」が「汝」に変わり得る可能性をもっている。たとえ相手が今は私のことを「それ」としか思っていないとしても、私が相手のことを「汝」と思い続けることでしか「私たち」の話し合いには辿り着けないわけですね。
土山 そのとおりです。そのように理解していることで、自分が他人を「それ」として見ていたり、誰かがそう考えているであろう場面に気づくことができます。インターネットで炎上している人を叩くという行為は、まさに相手を「それ」として見ている例です。先ほどご指摘をいただいた数の獲得を目的としたコミニケーションの問題も、対象を「それ」と認識してしまうことに関わる問題提起なわけですよね。
ーーまさしくそうです。「それ」としてみている他人とのあいだには、お互いに変化が生まれるような話し合いは成立しないわけですよね。かつて政治学者のカール・シュミットは、政治に重要なのは友と敵を区別することだと言いましたが、まずは自身の考えを持った上で、私と「汝」の違いを認識しようとすることからしか良好なコミニケーションは生まれない。
土山 そうですね。私たちの間で利害が対立する課題こそ、「私たち」の話し合いが必要なのです。
ーー意見の対立を超えて、友と敵の境界線を何度も引き直していく行為が話し合いの可能性だと考えると、改めて「揉める」ことの大切さを感じます。
土山 世の中には揉めることを良しとしない慣習があります。これまで受けた教育を思い返しても、揉めることよりも、既にあるルールを守ることが求められましたよね。私たちの社会は、自由はあるのに揉めにくい社会になっているのです。これまでやってはいけないことは法律で制限されていたわけですが、今は法律だけではなく社会の構造によって決められてしまいます。だって経営者が、デモに行くような人は雇わないと言うのですよ。信じられませんよね。少なくとも今は、支配されているということが意識されにくく、問題提起をすることがよしとされず、権力に従うことが良いという社会なのです。
ーー揉めることが苦手な私たちが、ちゃんと揉めるにはどうすればいいでのでしょうか。
土山 まずは、自分は揉めないとしても、揉め事を起こす人や問題提起する人のメッセージを認めてあげるところから始めなければいけません。自分が共感するか共感しないかというのはさておき、とにかく問題提起をしたということに対して敬意を払いましょう。
でも、問題提起に敬意を払えるようになるためには、少数者のメッセージへの共感が必要です。そうなると、いろいろな社会課題に対する話し合いの場、話し合いの機会がたくさんあることが望ましくなりますよね。ネガティブな「それ」の世界の問題点を受け入れながら、「汝」との関係を意識したつなぎ・ひきだす対話と問題提起への理解を広げていくことです。問題提起を見たときに「誰かが迷惑しているのだな」ではなくて、「時間を使っても伝えたいことがあるのだな」と、少数者の問題提起への価値に気づくことが第一歩ではないでしょうか。
ーーまずは周囲に存在する問題提起に関心をもつ。それなら明日からでも実践できそうです。
土山 もちろん揉める以外にも問題提起の形はたくさんあります。例えばデモ活動もシュプレヒコールを上げるようなものではなくて、LGBTQのレインボーウォークのように、みんなで楽しもうという形式もありますよね。以前私が住んでいたアイルランドの市民マラソンでは、仮装して走る人が「完走できたら一緒に市民団体へ寄付しませんか」と呼びかけるんです。そのような楽しい社会への関わり方がもっとあっていいと思います。
ーー社会参加にはたくさんの方法がありますよね。
土山 でもそうやって面白くすると、ふざけているのか、真面目にやれ、と言われてしまうでしょう。少し変わったことをやると世間に怒られますよね。変えていけない社会であることが、いろいろな不利益を生んでいます。だからこそ、いざというときに揉められるようにしておくことです。うまく仲良くなることではなくて、うまく揉めてうまく治められるようになるのが政策的なコミニケーション能力なのではないかと思います。だから、私にとって対話と議論というのは明確に区別できるものではなくてシームレスなものなんです。
ーーなるほど。
土山 揉められるようになると、支配されているかもしれない自分に対して敏感になれます。私は割と揉めてしまうほうなので、コストとエネルギーの要る人生だなと思いますが。(笑)
ーーでも、揉めないと世の中は変わりませんからね。
土山 みんながみんな、そういう生き方しなくてもいいとは思います。ただ、揉めたくないと思っていても、自分の生命や大事なものが脅かされることは誰にでも起こり得ます。そのときに揉められる武器は持っておいたほうがいいかもしれませんね。
ーー話し合いは、ちゃんと揉めてちゃんと治める練習の場なのかもしれないですね。私とあなたは何を考えていて、私たちの違いはどこにあるのか。話し合いの着地点を探る時間こそが大切なんだと感じました。
土山 そのとおりですね。話し合いは学びの場だと思います。私は我慢ができず喋ってしまうタイプなので、コーディネーターはできてもファシリテーターはできないのですが、どんな人にも「つなぎ・ひきだす」姿勢が求められます。
ーー「つなぎ・ひきだす」という価値観を、その人に合ったかたちで出力していくということでしょうか。
土山 そうですね。自分のキャラに合った力を身につけて欲しいと思います。
ーーこれからは話し合いの中の「対話と議論」のバランスに自覚的になれるような気がします。今日は非常に有意義なお話をありがとうございました。