コミュニティデザインの現在地を探るー2020年以後の話し合いの行方
まちづくりのワークショップや住民参加型の総合計画づくりが全国各地で実施されるなど、近年、地域づくりの現場ではワークショップの手法が定着、すっかり市民権を得た感があります。その「住民参加」と「話し合い」の時代を象徴的に体現してきた一人が、コミュニティデザインを広く世に知らしめたstudio-L代表の山崎亮さんです。
人と人がつながる仕組みをつくり、住民たちが地域の課題を自らの力で解決することを目指すコミュニティデザインは、どのような社会的背景の中で求められ、いかにしてコミュニティを再生してきたのか。また、「話し合い」はどこから来て、どこに向かうのか。山崎さんとともに、コミュニティデザインの歩みを振り返りつつ、「話し合い」が当たり前になった時代の“これから”を探ります。
studio-L 代表 山崎亮さん
山崎亮(やまざきりょう)
studio-L代表。関西学院大学建築学部教授。コミュニティデザイナー。社会福祉士。
1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博士(工学)。建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い。
著書に『コミュニティデザインの源流(太田出版)』、『縮充する日本(PHP新書)』、『地域ごはん日記(パイインターナショナル)』、『ケアするまちのデザイン(医学書院)』などがある。
著書一覧はこちら。 https://note.com/yamazakiryo/n/n5e1ea1f4979e
YouTubeチャンネルはこちら。 https://youtube.com/c/山崎亮99
震災を機に、時代の最前線に押し出されたコミュニティデザイン
――今日は、地域再生のキーパーソンであり、コミュニティデザイナーとしてご活躍されている山崎さんに「よい話し合い」をテーマにお話を伺いたいと思います。今や、住民参加によるまちづくりやワークショップは当たり前となりましたが、その過程においてコミュニティデザインが果たした役割はとても大きかったと感じています。当初、山崎さんは多くのメディアで取り上げられるなど、かなり派手に登場されていた印象がありますが、社会的な背景も含めてコミュニティデザインが求められた理由をご自身ではどのように捉えていますか。
山崎:コミュニティデザインがメディアで取り上げられるようになったのは2011年ですが、その年に東日本大震災があったことが大きかったと思います。震災後のコミュニティの在り方を考える議論の中で、なにやらコミュニティデザインというものがあるらしいと僕らの仕事に白羽の矢が立ったのでしょう。たしかに、当時は派手に登場していたなと思います。(笑)ただ、震災を機に何か特別なことを始めたわけではありません。僕は2005年にstudio-Lを立ち上げて、コミュニティデザインを手がけるようになるのですが、当時もそれまでと同じことを続けていたに過ぎません。やることも、地域に入って住民にヒアリングをして、ワークショップを行い、チームビルディングしてサポートするという、とてもシンプルなことでした。まだ当時は無名で、コミュニティデザインのようなものが社会にあまり知られていなかったがために各方面に広く紹介されることになったのですが、その結果、これまで関わることのなかったさまざまな領域の方々からも問い合わせをいただくようになりました。そういう意味では、やはり震災を機に、話し合いの場やコミュニティデザインの場があちこちに生まれていった印象がありますね。
――場所によっては既に行われていた住民参加による町づくりやワークショップが、震災を機に加速した結果、山崎さんのコミュニティデザインが時代の最前線に押し出されたということなんですね。

山崎:そうですね。2011年の震災を待たずとも、すでに私たちの社会はさまざまな課題に直面していました。例えば、日本の総人口は2008年に初めて減少に転じたのですが、1億3000人弱まで増えたスピードと同じペースで今後、人口が減少していくと予測される中で、これまでのような行政任せの町づくりでは役所は立ち行かないし、ハコモノをつくれば地域が潤うみたいな発想も成り立たないというようなことは当然ながら言われていたわけです。社会の問題が複雑化する中で、ひとりの建築家が立派な建物を建てて何かが解決する時代ではないことも分かっていましたし、さまざまな領域の専門知識や経験を統合した新しい知の必要性もすでに指摘されていました。そうしたモヤモヤとしていたことが震災を機に先鋭化し、もうやらなきゃダメなんだ、真剣に社会課題と向き合わなきゃいけないんだとみんなが動き始めたのが2011年だったと思います。
東日本大震災は来たるべき未来を10年早めたとよく言われますが、日本ではそうした時代を先取りするような大きな出来事が十数年ごとに起きていて、僕がコミュニティデザインを意識し始めた1995年の阪神淡路大震災もそうですし、現在の新型コロナウイルスのパンデミックもまた後世では変化の起点として語られるような気がしますね。
2つの分水嶺のあいだにとどまる英知
――もともとランドスケープデザイナーだった山崎さんが「コミュニティ」に興味を持ち始めたのは、阪神・淡路大震災の時に建築やランドスケープという「器」が崩れ去った瓦礫の中で協力し合う人々の姿を見たからだと聞きました。でも一方で、ご著書には「もともとワークショップを胡散臭いものだと思っていた」とも書かれています。改めて聞きたいのですが、山崎さんがコミュニティデザインを始めたのは、なぜだったのでしょう?
山崎:専門家が頑張れば頑張るほど、市民は専門家を頼るようになるという構図を意識し始めたからでしょうか。というのも、大学院生の時に読んだイヴァン・イリイチの『コンヴィヴィアリティのための道具』という本に書かれていた「2つの分水嶺」の考え方が頭にこびりついていたんです。そこでは、医療や教育、建築が技術革新するに従って、人々の暮らしの豊かさや快適度は右肩上がりで上がっていくけれども、一つ目の分水嶺に差しかかると少しだけ人々の快適度が下がり、さらに二つ目の分水嶺も超えて技術革新していくと、人々の快適度は更にどんどん下がっていくのだと指摘されていました。イリイチはアメリカの医療の場合では1955年に第二の分水嶺を超えたと言っているのですが、その時に何が起こったかというと、医者がどんどん新しい病気を発見するようになったんです。それまで名前がついていなかった病気に名前がつくようになって、人々はどんどん病院にかからないといけないようになった。かつてなら子どもが熱を出せば、お母さんが介抱していたし、ちょっと風邪をひいても卵酒を飲むという家庭医療もあり得たけれど、専門家が頑張りすぎた結果、人々はすべてを専門家に頼らざるを得ない状況になってしまいました。
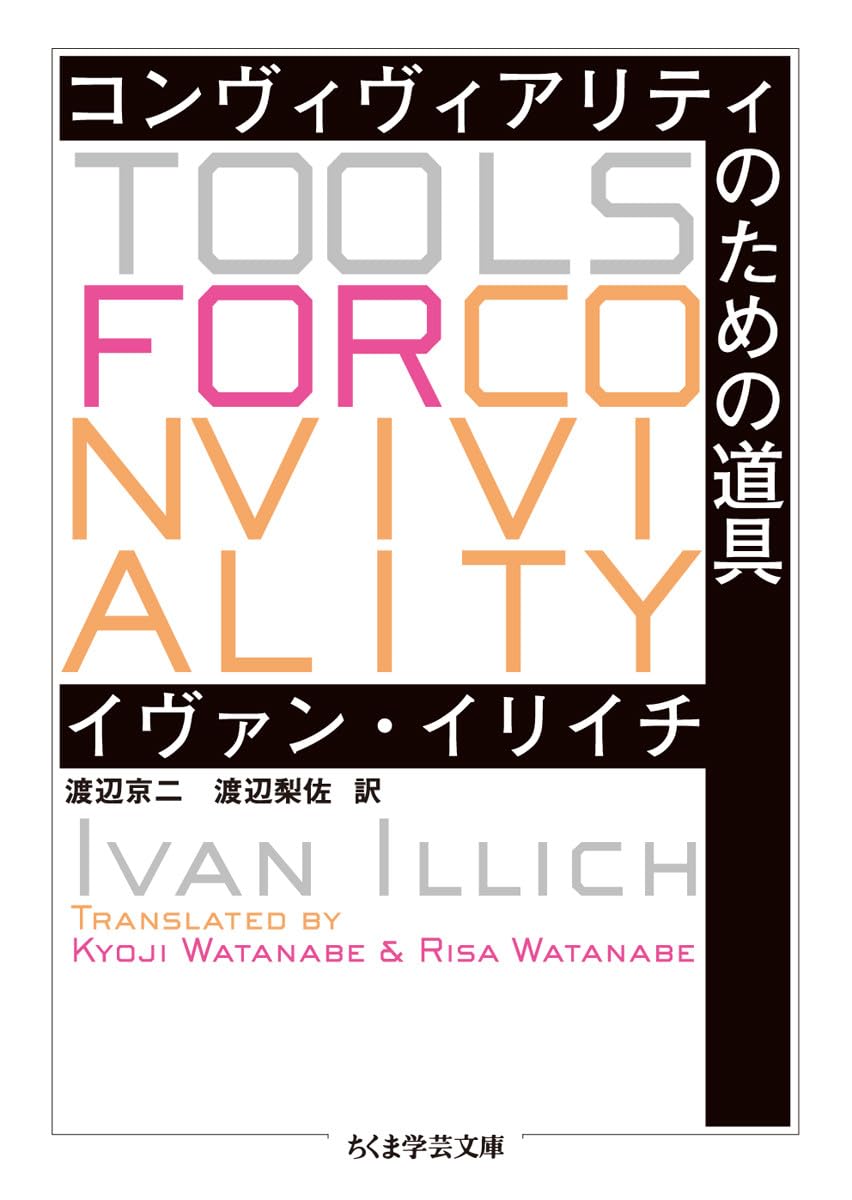
『コンヴィヴィアリティのための道具』イヴァン・イリイチ (ちくま学芸文庫)
この構図は、建築領域でも同じです。昔の民家は土間を叩いたり、屋根の葺き替えに至るまで地域の人が総出でやっていたので、集落には必ず大工仕事が得意な人がいました。ですが、専門家が手をかけ過ぎると素人がまったく手を出せない建築になってしまいます。雨漏りがしたり、屋根瓦が飛んでも改修の仕方が分からないから、そのたびにお金を払って専門家に来てもらわないといけないし、壁に絵をかけたいと思ってもコンクリートの打ちっぱなしだと、どうやって絵をかけたらいいのか分からない。それは本当に住みやすい家なんでしょうか。そういった専門性の問題に自覚的になった時に、むしろ胡散臭かったのは第二の分水嶺を超えてまでビジネスをしていた専門家の方じゃないかと思うようになったんです。そう考えると、ワークショップに感じていた胡散臭さは消えていきました。
――専門家としての在り方を見つめ直したのですね。
山崎:そうです。専門家としては、イリイチの言う第一の分水嶺と第二の分水嶺の間の高台に留まるような関わり方が、コミュニティデザインの基本的な態度です。だから、僕らの仕事は極めて素人っぽいやり方なんです。住民を集めて話し合いを進めていく方法についても、その手順が分かれば誰にでもできることですし、なにより僕らは最先端の機器も持たず、模造紙と付箋だけを持って地域に入っていく。かなりアナログな方法なんですが、あえて専門家が頑張りすぎないようにしているんですよ。
――わざと専門家っぽくならないように心がけられていると。

山崎:はい。それこそ『コンヴィヴィアリティのための道具』ではこう言われています、なんて話はワークショップでは絶対にしません(笑)。僕らにとっては、どれだけ分かりやすく一般の人向けにお話をできるかが大事なんです。
――なるほど。しかし、そうは言っても山崎さんのワークショップには、専門性やノウハウのようなものがありますよね。以前、山崎さんが登壇されていたイベントで、各地の事例をまとめたおびただしい数のスライド資料を見て驚いたことがあります。(笑)あれを見ると、山崎さんの頭の中ではワークショップが始まった瞬間にいくつもの選択肢や方向性がイメージできているのではないかと思ったのですが。
山崎:自分のワークショップをノウハウとしてちゃんと説明できるか分かりませんが、この地域でこの条件だったら、こんな方向性かな?というイメージは、地域に入る前に10種類ぐらいは頭の中にあります。それはあくまでも柔らかいアイデアですが、実際のワークショップで住民の方々が話すのを聞くと、この人が言っているのは自分が持ってきたAのアイデアにBを足したぐらいの話かなとか、あの人が提案しようとしているのはCとDの要素にEを少しふりかけた感じかなといった具合に、なんとなく判断ができるんです。それならば、イギリスでこういうことをやっている人たちがいますよと言ってみる。「そうや、俺のやりたいことはそういう感じや!」と返して来たら、だいたい合ってたなとなるし、「いや、ちょっと違うんだよね」と言われれば、あぁ違ってたかと案を引っ込める。そうやって一人ひとりの発言に対して、用意したアイデアを物差しのように照らし合わせていくので、僕にとってのファシリテーションはリトマス試験紙みたいな感じなんです。アイデアに対する反応をみながらチューニングをしていき、最終的には住民の方々がやりたいと思う方向の先にある地域づくりへと統合させていくんです。
――住民の方が思い描くことを、具体案に落とし込んでいくようなイメージでしょうか。
山崎:そうです。studio-Lのワークショップに参加すると、アイデアが思いつくんだとか、いいことが言えている気がするという気持ちで帰ってもらう。そうすると、次のワークショップにも来てくれるんですね。最終的に「これはみなさんが言ったことですよね」という風になればいいわけなので、「このアイデアは俺が言うたやつや!」と言える人が地域に何人増えるかが僕らにとっては重要なんです。なので、事前に持っていたアイデアをこちらから提案するということは一切しないですね。
――ワークショップで住民の方々に主体性が生まれると、専門家がいなくても、自分たちだけで地域の未来について話し合うことができるようになるのでしょうか。
山崎:あり得ると思いますし、僕らはそこを目指したいと思っています。それがファシリテーションにおける第一と第二の分水嶺のあいだに留まる英知だと思います。住民たちに主導権があり、自分たちで地域のことを決めていくことができるんだと再認識してもらうことが僕らの仕事の目的であり、コミュニティデザインの目的なんです。
「話し合い」はどこから来て、どこに向かうのか
山崎:実は今、これまで僕らが取り組んだコミュニティデザインのプロジェクトやその手法を本にまとめているところなんです。全体で1000ページほどの辞書のような厚さの本で、第1部では約70のプロジェクトを文章と写真、図録で説明し、第2部では人集めのチラシからワークショップで使用するツールなど約80の手法を整理して解説する予定です。普段からコミュニティデザインについてご質問を受けることが多いのですが、僕らもどれが自分たちのオリジナルか分からないままに、現場に応じて次から次へとツールなどを開発してきた15年間の蓄積があるので、それを一覧できるようにしたいなと考えています。
――それはすごい。これまでのコミュニティデザインの全てが明かされるのですね。studio-L設立からの15年で話し合いがどのようにアップデートされてきたのかが気になります。
山崎:明確に時代区分までは分かりませんが、ワークショップというものに慣れた人が増えた15年だったとは言えるでしょうね。2005年に始めた当初は、まだワークショップをやったことがない人が多かったので、どの地域に行っても「なんだ、それ!」「その横文字はなんだ?」とよく言われたものです。それまでは「話し合い」というと、ロの字型のテーブルで役職のえらい人が上座に座る形で、喋る人もある程度決まっていて、話す主題も事前にきっちり決まっているのが普通でした。その感覚から抜け出せない人たちがたくさんいて、「俺の話を聞け」というスタイルだったので、そういう場ではありませんよと伝えるところから始める必要があって、2010年ぐらいまでの5年間はそこに苦労していた気がします。
それが、冒頭でお話ししたように2011年以降、各地でたくさんのワークショップが開催されるようになって、「人の意見を否定しない」とか「勝ち負けをはっきりさせるディベートではない」といった話し合いのルールを理解する人がかなり増えました。むしろ今ではワークショップアレルギーになるほどたくさんの話し合いをやらされた人たちも少なからずいるはずです。そういう意味では、いよいよ次の段階に行かないといけないんじゃないかなというのが今の流れだと思います。
――次の段階とは、具体的にはどういうことでしょうか。
山崎:日本全体として話し合いについての理解は広まってきたので、例えば大学の講義なんかもアクティブラーニング(講師による一方的な講義ではなく,学修者が能動的に参加する学習法)に変わっていかなければいけないだろうし、中学校や高校でグループディスカッションを経験してきた若い世代がもう社会に出てきているので、さまざまな制度や体制を変えていく必要があると思うんです。ただ、その時に問題となるのは、話し合いの感覚が世代によってだいぶ違うことです。

ゆとり世代よりも下の世代の人たちはアクティブラーニングのネイティブなので、机をパッと移動させてグループワークをして、内容をみんなと共有するなんてのは当然なんですね。「対話」や「話し合い」の価値も当たり前のように分かっていて、話し合いを通して自分の意見が変わったり、新しい発見があることにこそ意義を感じられる世代なんです。それに対して、40~50代の世代になると、「自分の意見を通したら勝ち」みたいな感覚があるので、「自分の意見が変わらなかったら負け」と思っている若い世代との開きが大きいんです。その両者がワークショップで出会うと、若い世代は「新しい意見を聞けた」と満足できるんですが、上の世代は「今日も俺の意見を通してやったぜ!」と思いこんで帰っていくので成長が起きません。これから先、議論に勝ったと勘違いして帰っていく人たちが量産されていくのかと思うと、ちょっとマズいなと思っています。
――一部の世代だけが勘違いする土壌ができあがってしまっていると……。
山崎:もうそれは、フワフワの心地いい土壌ですよ。若い世代は、人の意見を否定しないという話し合いのルールが身についているので、それこそニコニコして受け止めてくれちゃう。で、おじさんの方は「なんだ、最近の若い奴は主張がないなぁ」とか言って、ちょっといい気分になってしまう。マズいですよ、ほんと。僕も同じ世代なので、常に自分をアップデートしておかないとヤバいなと思っています。
――若い世代と山崎さんの世代の間に、「話し合い」の分水嶺があるのでしょうか。
山崎:僕らの世代は、弁証法的止揚のようなものを一部の人が信じていた団塊の世代と、今の若い世代のちょうど狭間です。弁証法的止揚というのは、あなたがAと言うなら、私はあえてBという反対意見を提示して、それがぶつかることで新しいCという意見を生もうという考え方です。僕の両親は、まさにその思考だったので、家の中では常に議論を吹っかけられながら育ちました。「今日は何が食べたい?」と聞かれて、「焼肉」と答えたら、「その論拠は何だ?」と言われたりする。社会の中でもこの世代は人口が多いので発言力があって、その下の世代は何を言っても論破されるので頭が上がらないという状態があったようです。ただ、僕ら団塊ジュニアは団塊世代とは親子の関係なので、「おとん、おかん、ウザいぞ」と言えるわけです。だから、僕らは団塊の世代に引導を渡して、ある種、「話し合い」を変える分水嶺となる使命感のようなものを持っていた世代ではあると思います。
――団塊の世代の議論好きは、なんとなく心当たりがあります。でも、それは日本の伝統的な話し方ではなさそうですよね。
山崎:近代的な話し方だと言えるでしょうね。民俗学者の宮本常一さんによると、かつての日本人の話し合いは、みんなが疲れるまで話し合って終わるというかたちだったようです。というのも、宮本さんがどこかの地域に行って、江戸時代の文書を見せてもらおうとしたら、ここには家同士のもめ事なんかも記載されているから自分の一存では決められないと。ついては集落の人間を集めて話し合いをするから、明日の夜に来てくれと言われ、行ってみたら話は堂々巡りで結論が出ない。それで、明日また話し合いをするから来てくれと言われ、行ってみたら、やっぱり結論が出ず、それが4日も続いたそうです。結局、話し合いはまとまらなかったようですが、4日間文句も言わずに座っていて、悪い人じゃなさそうだから見せてもいいんじゃないかということで、最後はみんなが同意したと。日本の話し合いというのは各地でそれぞれ特徴があったようですが、概ねこんな感じだったようですね。
いいアイデアよりも、協働したくなる関係性が財産になる
――人の意見をひきだし、つなぐことに長けた山崎さんが、実は“否定”や“論破”の多い環境で育ったというのは、興味深いお話です。てっきり生まれつきのファシリテーター気質なのかと思っていました。
山崎:ぜんぜん、真逆です。おそらく学生時代の友人たちは、僕がコミュニティデザインをやっている姿をメディアで見て、嘘っぽいと思っているに違いありません。(笑)今思い返しても、お恥ずかしい限りです。とにかくぜんぶ否定から入っていましたから。両親のコミュニケーションが染みついていたんだと思うのですが、誰かが何か言ったことに対して、すぐに「でもね…」と言っていました。それと、親が転勤族で、中学時代までは転校を繰り返していたので、新しい環境に入っていく時に、弱く見られないように無意識の自衛策として、威圧的に喋ったり、否定から入って自分の価値を認めさせたりというような強がり方を身につけてしまったというのもあったんだと思います。
それが、ワークショップに出会って、さまざまな話し合いに関わる本を読む中で、徐々に気がついていくんですね。「yes、and」の肯定から入るコミュニケーションの本を読んでは「あぁ、自分はぜんぶNoから入ってたな」と反省したり、あれもダメだったのか!これもダメだったのか!だから嫌われてたのか!というふうに。(笑)でも、その時に自分のコミュニケーションを変えようと思ったのは確かです。かなり恥ずかしい青年時代を送りましたが、30歳を越えるあたりからちょっとずつ相手の意見が肯定できるようになり、ようやくこれでいいかなと思えるようになったのは、本当にこの10年ぐらいのことなんです。
――ある意味、ワークショップやコミュニティデザインが山崎さんを変えたんですね。でも、相手の意見にあえて反対意見を提示する弁証法的止揚にもその意義はあったと思うのですが、なぜご自身のコミュニケーションを変えようと思われたのですか?

山崎:相手に対して反対意見を提示するということは、否定する理由をちゃんと考えないといけないし、否定された方も頭を働かせなきゃいけなくなるので、両者が深く物事を思考するという意味では、意義があるとは思うんです。逆に、肯定から入ると、「いいね」と言った方はもうそれ以上考えなくてもよくなるわけですから。なので、両者が議論した掛け合いの中から新たな意見が生まれると信じていたのですが、人間ってそんなに強いもんじゃないよなと思うようになったんです。やっぱり人間は、否定された相手とは喋りたくなくなるし、そんな相手と何かを一緒にやりたいとは思えなくなる。たとえ議論の末に素晴らしいアイデアが出たとしても、一緒にやりたいと思う人が誰もいなくなったのでは意味がないなと。そこのジレンマに陥っていたのが、かつての学生運動だったと思うんです。お前と議論して、俺は負けた。たぶん、お前のアイデアの方が正しいと思う。でも、俺はお前のことが嫌いになったので、一緒にはやりたくない、と。だから、かつて学生運動では社会は変えられなかったんじゃないでしょうか。
「いいね」だけではいいアイデアは生まれないとよく言われます。でも、僕はお互いに肯定し合って褒め合って、浮かれている状態の方が潜在的にはすごく大事だと思うし、「じゃあ、やってみよう」「くだらないかもしれないけど楽しんでみよう」というところからスゴいものが出てくることもあるはずです。だから、議論をしていいアイデアを生み出すよりも先に、「この人とやってみたい」と思えるようなコミュニケーションをつくる方が大事だと思っています。
――相手を否定しない話し方は、人生も豊かにしてくれそうですね。
山崎:それはもう圧倒的に変わりますし、人生が楽しくなりますよ。「山崎さんっていい人ですね」と言われることが30歳頃までは皆無だったので、慣れない頃はちょっと落ち着かなかったですけどね。(笑)「僕は肯定しかしていないんだから、あなたは騙されてるだけだよ」とずっと思っていましたが、30代から20年ぐらいこのコミュニケーションを続けて、いい人と言われるようになると、「俺って、実はいい人だったのかもしれない」と自分も騙されるようになるんです。
こういうコミュニケーションの問題は、男女関係でも同じだと思います。否定ばかりする相手とずっと一緒にいたくはありません。常に肯定から入る話し方が癖になっている人は、やっぱりモテるだろうし、仕事も増えるだろうし、いろんなチームにも入れてもらいやすくなるはずです。
だから、僕は自分の子どもたちが小さい頃には、偏差値が高いとか、正しいことが言えるとか、そういうことにあまり価値を持たないで欲しいと伝えていました。そうではなくて、友達がみんなでご飯を食べている時に、「あれ、山崎おらんやん」「アイツ呼ぼうや」と言われるような人になって欲しいと。いくら頭脳明晰で頭が良くても、AIのディープラーニング(人工知能が人間の手を必要とせず、自分で考えて答えを出せるようにしていくこと)にいずれ取って代わられる時代がくる。その時に必要なのは、否定しないコミュニケーションのようなもので、「あいつがいたら面白くなる」と思ってもらえるかどうか。それがものすごく大きな財産になると思います。
否定しない場と徹底的に否定する場を使い分ける
――否定しない話し合いが大切な一方で、自分の意見をはっきりと伝えないといけない場面もあります。私たちも相手の意見を尊重するコミュニケーションを心がけているんですが、ときに自分の軸がないのではないかと不安を抱いてしまう時もあるんですよね。
山崎:今、二つほど考えたことがあります。一つは、自分の軸がなければならないというのは、誰かがそういう呪いをかけているんじゃないかということ。本当に自分の軸というものが必要なのか、もう一度問い直してみてもいいかもしれません。自分には軸がないし、何も主張することがないという人たちばかりが住んでいる地域がダメだったことが今までに一度でもあっただろうかと。いつも考えが揺れていて、あの人の話を聞いたら感動して「たしかに、そうっすね!」と思い、反対の意見を聞けばまた感動して「それもそうですね!」と言っている人たちばかりがいる地域って、僕は悪くないなと思います。志なんてない方がいい地域ができるんだよと信じ込んじゃってもいいのかもしれないなと。
もう一つは、もう少し器用になってもいいのかもしれません。ある条件の時には相手の意見を否定せず、仲良くなったり、いい気分になってお互いを鼓舞し合ったりして活動に結びつけていく必要があるけど、違う条件が揃った時にはむしろ意見をぶつけ合ってみるというように、コミュニケーションを使い分けることができるとよいかもしれませんね。例えば、studio-Lの打ち合わせや会議は、めちゃめちゃ否定の場なんです。特にプロジェクト前の発表は大変で、僕が真ん中にいて、コアメンバーがズラッと並んでいるところでスタッフは発表をしなきゃいけないのですが、話している途中で「分かった分かった、もう先が読めた。で、それは何が面白いの?何が新しいの?」って突っ込まれまくっています。

――それはかなりのプレッシャーですね(笑)
山崎:ウチのスタッフは否定する人が現れた現場でもファシリテーションをやらなきゃいけないので、怖いおじさんに怒鳴られて言葉が出なくなるようでは仕事にならないんです。いいねと言いあうだけの会議をやっていると、いざ現場にでた時にフリーズしちゃうんですね。
スタッフもそれを分かっていて、僕らに徹底的に否定されながら、反論したり、別の話題に持ち込んだりしたりしながら、どうにかその場をすり抜ける術を身につけるんです。
なので、否定しないコミュニケーションが適する領域と否定してもいい領域を見極めて、そこを柔軟に行き来できるような人になることを考えてもいいかもしれません。
――僕らは龍谷大学の政策学部で否定しないコミュニケーションや合意形成を図る技術を学んだんですが、社会人になるとそれだけでは弱いなと感じることも多々あります。今のお話を聞いて、意見をぶつけ合う力と合意形成を図る力の両方が必要だと改めて感じます。
山崎:僕からすれば、否定しない話し方が身についている今の若い方々は大先輩で、羨ましいのですが、それゆえの不安もあるんですね。僕から1つアドバイスをするならば、誰にも嫌われないで存分に否定してみる、あるいは自分の軸をつくってみる方法として「本との対話」があります。僕は本を読んで、そこに書いてあることを否定したり、論破したりしながら赤ペンでびっしり書き込んでいくというのが癖なんですが、それだと自分の性格の悪さが誰にもバレずに否定の練習ができるんですね。
例えば、ハンナ・アレントの『人間の条件』は公共政策の必読書だと思いますが、それに対して論理がどう矛盾しているかとか、現代社会にはどう通用しないかみたいなことで議論をふっかけて、アレントをディスりまくるわけです。そうやって知の巨人と言われるような人たちに議論をふっかける。まあ、たいがいは負けるんですけどね。(笑)
自分の軸を確かめたり、自分の論理を組み立てるためには、否定しなきゃいけない時や自分の思いをぶつけなきゃいけない時があります。それを生身の人間を相手にやると嫌われちゃうので、そうならないために本を相手に壁打ちをするというのは一つの方法だと思います。
――考えを整理できないとき、いちど他者の意見を介すると自分との差異がくっきりと浮かび上がるような経験には心当たりがあります。私が私であるためにも、場面にあったコミュニケーションを大切にしていきたいと思います。
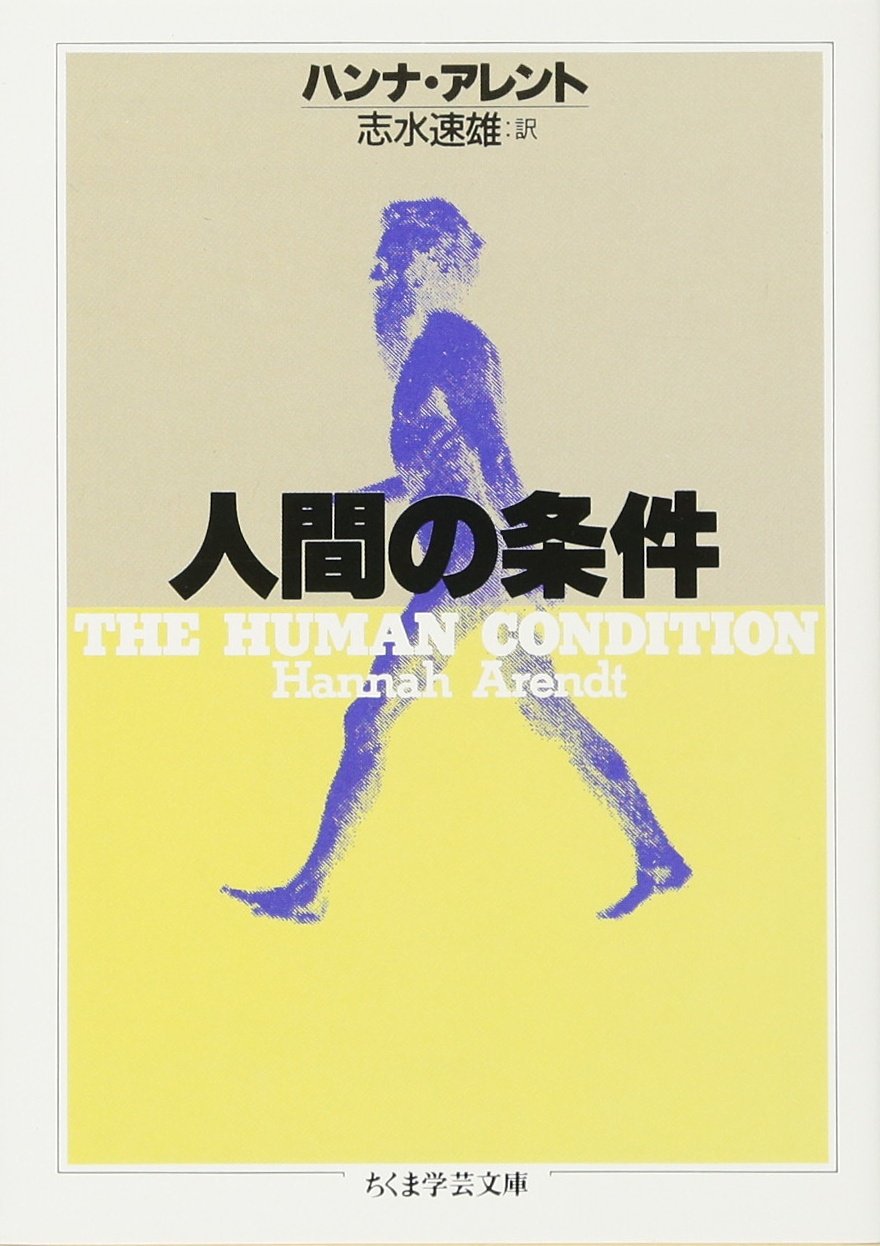
『人間の条件』ハンナ・アレント (ちくま学芸文庫)
2020年以後の話し合いの形式
――15年間のコミュニティデザインの取り組みを通じて、「話し合い」の限界を感じる場面はありますか?
山崎:「話し合い」だけでは足りないという気持ちは、かなり早い段階から持っていました。コロナ禍のオンラインワークショップでは、どうしても言葉と表情だけの話し合いになってしまい、参加者全員が同じ体験をする、いわゆる共時体験がつくりにくくなるので、この2年ほどはかなり試行錯誤しましたね。オンラインで集まった時にみんなで食べられるものをstudio-Lから事前に各参加者に送ったり、アイスブレイクの際に「家の中にある赤いモノを持って集合してください」と呼びかける工夫をしました。そのおかげで手法のレパートリーは増えましたし、参加者もオンラインでの参加に抵抗感がなくなったので、これからは対面とオンライン両方の参加スタイルを併せたハブリッド型のワークショップも行っていく予定です。
――対面が制限されたことでワークショップの幅も広がったのですね。
山崎:さらに言うと、録画しておいた動画をいつでもいいので見ておいてもらうワークショップもできるようになります。例えば、病院を建てるプロジェクトであれば、世界中のおもしろい病院の事例などを紹介した動画をYouTubeにアップしておいて、参加者は都合のいい時に見て、思いついたアイデアや言葉をどんどん書き込んでいってもらう。そこに返事を書き込んでいくと、ちょっとした対話も生まれてきます。この方法なら世界中どこからでも好きな時に書き込めるし、ログもずっと残っていく。こういったオンデマンド式のワークショップができれば、通常の「対面同期型」のワークショップと「オンライン同期型」、「オンライン非同期型」をプロジェクトに応じて使い分けたり、組み合わせて複合的に行うことができます。そして新しい領域として、対面なんだけれど同じ時間に集まらない「対面非同期型」という形式もあり得るかもしれません。例えば、空き店舗や空き家を1週間開けておき、そこに付箋と模造紙を置いておいて、地域の人たちが好きな日時に訪れ、居合わせた人同士でちょっと話をしたりしながら書き込んだり、ペタペタ貼って帰っていくイメージです。コロナ以後の話し合いは、この4種類の形式を適宜組み合わせた発想が可能になるのでないでしょうか。
――コロナを機に、空間だけでなく時間が設計の対象になり始めたと。これまで当たり前だった対面同期型の場づくりを問いなおす機会にもなりそうですね。
山崎:まさにそうなんです。僕らも対面のワークショップが一番いいにきまっていると思い込んでいたけれど、実際の話、例えば平日の夜7時に公民館に来ることができる人って、高齢者か、仕事後でも参加する熱意のある人、親が連れてきた子どもぐらいだったんですよ。それがオンラインになると、仕事帰りで疲れていても家からであれば参加するとか、残業中でもタブレットで喋るぐらいならできるとか、子育て中の母親、ヘルパーがいない高齢者、遠くに住んでいる人など、参加できる層がめちゃくちゃ増えるんです。

――冒頭でもコロナ禍が大きな変化の節目だとおっしゃっていましたが、まさにコミュニケーションをとりまく環境が大きく変化しているんですね。今後も話し合いの形式が多様化したり、新しいコミュニティデザインのかたちが増えていきそうな予感がします。
山崎:よい話し合いというのは、言葉のやりとりだけではなく、みんなの感覚を揃えていく過程を含めたものだと思っています。それはちょっとした目配せであったり、みんなの飲み物を取ってきてくれる人がいたりするようなことです。話し合いを進めると、どうしても口の上手い人や論理的に話ができる人が強くなってしまうことは常に課題なんです。
そうした時に、いろんな参加形式を選択できれば、言葉の優位性を相対化できると思うんです。話し合いの手法が多様化していけば、けっこう面白いことが生まれるんじゃないかなという期待感を持っています。
――今後もまだまだ山崎さんは忙しくなりそうですね(笑)
山崎:本当は僕らが忙しくなっているようではダメなんですけどね。本来は僕らの仕事が減っていくことが、コミュニティデザインの成果なわけですから。studio-Lの分厚い本が出版されて、それさえあれば専門家に頼らなくてもいいということになれば、僕は陶芸家にでも転身しようと思っていますが、今のところはまだまだ踏ん張りたいと思います。
――今日は、本当に貴重なお話をいただきありがとうございました。