ただここにあること、遠い誰かとつながること
藤本 遼(ふじもと りょう)
株式会社ここにある代表取締役/場を編む人
1990年4月生まれ。兵庫県尼崎市出身在住。「株式会社ここにある」代表取締役。「すべての人が楽しみながら、わたしとしての人生をまっとうできる社会」を目指し、さまざまなプロジェクトや活動を行う。「いかしあう生態系の編み直し」がキーワード。現在は、イベント・地域プロジェクトの企画運営や立ち上げ支援、会議やワークショップの企画・ファシリテーション、共創的な場づくり・まちづくりに関するコンサルティングや研修などを行う。さまざまな主体・関係者とともに共創的に進めていくプロセスデザインが専門。代表的なプロジェクトは「ミーツ・ザ・福祉」「カリー寺」「生き博(旧:生き方見本市)」「場の発酵研究所」「武庫之のうえん」など。『場づくりという冒険 いかしあうつながりを編み直す(グリーンズ出版)』著(2020年4月)。
遊びのような仕事をつくる
藤本:よろしくお願いします。遼ちゃんとお呼びください。僕は兵庫県の尼崎市出身で今も尼崎に住んでいます。関西大学を卒業後は新卒でNPOに就職をしました。いわゆる中間支援という仕事で、NPOの支援やまちづくりなど、町に関わるいろいろな活動を2年半した後に25歳で独立しました。その後、29歳まで4年ほど個人事業を続け、2019年の11月に、株式会社ここにあるという会社を立ち上げたんです。基本的には尼崎市を中心に、行政や電鉄会社、不動産会社、商業施設、地域の人たちと一緒に町の課題を解決するような少し変わった場を立ち上げる仕事をしています。
——独立される前からまちに関わるお仕事をされていたんですね。
藤本:現在の活動は2015年の夏頃、塚口駅前にある商業ビルの一部を改修してイベントスペースをつくることから始まりました。200人ぐらいの人に関わってもらいながら場所をつくったことを機に独立したんです。前職でもまちづくりに関わっていたんですが、もともと独立心もあったので。わかりづらい活動なので最初はなかなか仕事につながりませんでしたが、少しずつお声掛けをいただくようになり、場の進行役であるファシリテーターとして呼んでもらったり、講演の機会をもらったりして、少しずつクライアントワークが増えていきました。
たとえば「地域に開いた高齢者向けのデイサービスをつくるために、まちの人をどのように巻き込んでいったらいいのか」という相談を受けて、コンセプトづくりからプロセス設計に関わりながら段々と仕事になっていった感じですね。今もそうなんですが、仕事をしながらもずっと遊び的なことをやっているんです。遊び的なものというのはクライアントワークではなく、自分で勝手にやっているということです。代表的な取り組みは、お寺でカレーを食べる「カリー寺」というフェスです。中平了悟さんというお坊さんとたまたま出会ったときに、僕がカレー好きなのでお寺を使ってカレーのイベントをしようという話になったんですよ。2016年から年に1回、例年500〜700人くらい集まるイベントを地域の人たちと一緒につくっています。お金をいただく仕事と遊びのバランスをとりながら活動してるような感じでしょうか。

——独立してすぐに様々なお仕事を手がけられていたんですね。お仕事に関わるスキルは大学時代や前職で身につけられたのでしょうか。
藤本:いや、完璧に独学ですね。前の職場でも市民参加型のまちづくりを支援するような仕事はあったんですが、新人がファシリテーションやワークショップの運営を任されるかといったらそうでもないので。実践経験は、仕事以外の個人的な活動の中で学んでいった感じですね。
——個人的な遊びの中でいろんな経験をされたってことですね。
藤本:自主イベントは2014年ごろから尼崎で始めてたんですよ。神社の社務所を借りたり、銭湯やカフェを借りたり。そういうイベントをやっていく中で仲間がちょっとずつ増えて、もっと自由に使える場所があったらいいよねって話になったんです。たまたまその頃にいいメンバーと出会えたので「尼崎ENGAWA化計画」というプロジェクトチームを立ち上げることになりました。僕と尼崎市役所の江上さん、GASAKI BASEというお店を運営していた足立さんの3人です。このメンバーが中心になって「amare(あまり)」というコミュニティスペースをつくろうという動きが始まったんです。
——自由度が高いみんなの居場所っていいですよね。一番最初にイベントをされたのか気になりますね。
藤本:最初のイベント..もう忘れちゃったんですけど。
——そうですか。(笑)
藤本:「ソーシャル」っていうキーワードがあるじゃないですか。当時はソーシャルビジネスとかソーシャルデザインとかって言葉が出始めた頃で、僕らもけっこう興味があったので、ソーシャルな活動に興味のある男子、ソーシャルメンズで集まる「ソーメンナイト」っていうイベントをやったのが最初かもしれないです。ソーメンナイトって言いながらそうめんを食べるっていう、めちゃくちゃくだらないイベント。
——面白い(笑)当初はお1人で企画をされてたんですか。
リノベーション-902x601.jpeg)
藤本:いや、まずは他所のイベントに参加して友達や仲間を増やすところからでした。そうじゃないと、なかなかイメージもつかめないし。そこで出会った仲間とつくった遊びの延長線上にいろんな仕事が入ってきて、今の取り組みにつながっている例も多いように思います。
——遊びがきっかけで仕事が生まれていったんですね。
藤本:今も仕事じゃなくて遊びをしている感覚です。仕事にするといろんなことが面白くなくなるじゃないですか。
——わかる気がします。
藤本:わかりますよね。おもろいからやってることも、これやらんとあかんとか、あれやれって言われたらなんか嫌な感じになる、みたいな。だから極力クライアントワークも自分たちの土俵に引き込むことを意識していて。いわばアート活動に近いと思うんですよ。アーティストはもう既に自分の描きたいものを描いていて、そこにパトロンがお金を払うみたいな感覚。そういう仕事のつくり方のほうが面白いと思っています。だから我々は何者で何をしているのか、スタンスやビジョンはかなり明確に伝えるようにしています。それが自主プロジェクトの端々に織り交ぜられているので、クライアントワークの場合も最初から大事なポイントを共有できる人が声を掛けてくれるんです。だから自分たちのやりたいことや大切にしている在り方からブレないでいられる。遊びであるってことは、すごく大事だと思います。
「ここにある」を表現するオルタナティブな世界観
——自分らしい在り方を大切にするということですね。藤本さんが大切にされているこだわりはどういったものなんでしょうか。
藤本:会社のホームぺージに大切にしたいスタンスを書いているんですが、キーワードはいっぱいあるんです。例えば、うちは商業施設とも仕事をしてるんですけど、予算かけてPRをして人をたくさん集めて終わりってのはどうなのかなと。当然、商業施設にとってお客さんが増えることは一つのゴールなんですけど、結局は「どういうふうに生きられると人は幸せなのか」みたいな前提を共有することが大事やなと思っていて。お客さんが単に増えるっていうことだけじゃなく、尼崎という土地だったら自分を表現できるんだとか、自分自身でいていいんだっていうことを感じられる場づくりの大切さをクライアント側ともすり合わせていくっていうか。それが結果としてお客さんの増加につながるというロジックを共有するのが大事だと思うんです。僕らの活動は、主体者というか自分たちで動いていく人をどう増やすかということに取り組んでいるし、そういう仲間をどうやって増やしていくのかが大切なんです。結局、誰かが社会が変えてくれるんでしょという話ではなく、自分たちで意思決定して楽しく動いていけるような社会がいい。そういう価値観を共有するために対話の場をつくったり、自分達のスタンスを言語化することを心がけています。
——ホームページに記載されている「大切にしている9つのこと」を拝見しましたが、それぞれの丁寧な言葉選びから藤本さんの思いが伝わってくるように感じました。文章の端々に「優しさ」があるというか。
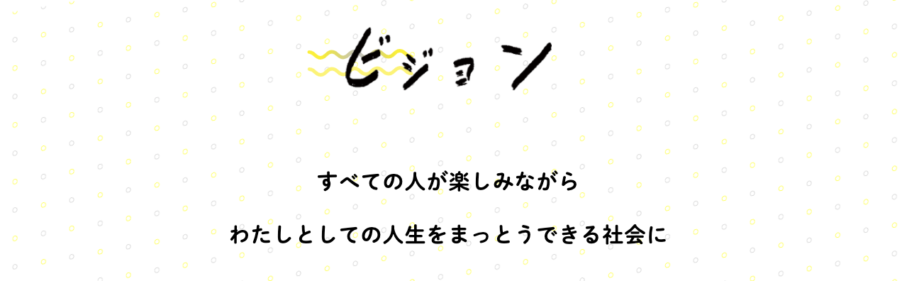
藤本:「弱さ」とか「受け入れられなさ」のような一見ネガティブだとされるものに価値があると認めたほうが生きやすいんじゃないかなと思っていて。今の社会って、やっぱりスキルや強みでつながる社会だと思うんですよ。専門技術があるから会社に採用してもらえたり役職が上がるみたいな。そういう強みでのつながりは今の社会においてたくさんあるんだけれども、弱さでつながることはあまりないような気がしていて。むしろ「弱い者は駄目だ」とか、「弱さを強さに変えないといけない」みたいな空気感のせいで弱さを表に出せない。弱さを隠した結果、病気や鬱になったり、犯罪や暴力が起こっているんじゃないかと思うので、そこは両輪で考えないといけないと思っています。
——「株式会社会社ここにある」というネーミングはまさに今のお話を表していますよね。現代社会を生きる私たちは、「ここにある」ことの難しさを考えなおさなければならない。
藤本:完全に宗教とかの領域ですよね。
——信じるものや仲間の存在は、そこに立っていられる理由になりますからね。
藤本:そうなんです。今の社会は信仰の対象が少ないのでみんなお金を信仰をするわけじゃないですか。けれどお金では完全に満たされてなかったり、安定しなかったりする。一方で仏教を学んだり週末に教会に行くという行為が日常になるかっていうとそれも難しい。だからこそ、人々の拠りどころをリデザインしないといけないと思ってるんですよ。僕がお寺に関わってるのは、お寺の旧来持っていた価値を現代的な意味合いにしたいという思いがあるからなんです。以前ルクア大阪という施設でお坊さんが若い女性のお悩みを聞く「坊主喫茶」というイベントがありました。そこである参加者の女性がインタビューで言ったんです。「お寺は怪しいから行かない。だけど商業施設のルクアは怪しくないから行くんだ」と。これはめちゃくちゃ面白いなと思うわけですよ。商業施設が人の拠りどころになるようなコンテンツやスタンスを提示できれば、現代的にはすごく意味があるかもしれない。僕も商業施設の場所づくりに関わっているので、今後チャレンジのしがいがあるポイントだなと思ってますね。
——面白いですね。自主的な取り組みだけじゃなく、クライアントワークに「ここにある」ための価値観をつなぎ込んでいく大切さを感じます。
藤本:じゃないと面白くないじゃないですか。何のために生きるのかが分からなくなるのが一番寂しいので。他には、ミーツ・ザ・福祉っていう、障害のある人と一緒にやっているフェスがあります。尼崎で2017年からやってるイベントなんですけど、障害があってもなくても楽しめるフェスを目指そうということで30~40人ぐらいで企画をおこなっています。運営メンバーの中でいわゆる障害者と言われる人たちが10名ぐらいいるのかな。障害者は基本的には支援される存在とされますが、そうじゃない状況をどうつくるのかについて考えています。出店が60~70店舗、ステージパフォーマンスが10組ぐらいあるのに加えて、健常者と障害者がコンビを組んだ漫才や、車いすのメンバーがやりたかった運動会企画なんかもやったりしています。
——非常にユニークなイベントですね。
このイベントは障害者のためにやってるイベントではないという点がめっちゃ大事な気がしていて。障害者を主役にしたイベントってあるんですけど、そうじゃないんですよ。障害があろうがなかろうが関係ないし、主役になりたい人もいれば、脇役になりたい人もいる。関わり方を自分でちゃんと選べる小さな世界をつくることが大切なんです。

——「常識」というラベルを剥がしていくイベントなんですね。こういう世界のほうが楽しいよねということを、説得的に語るわけじゃなくて、無条件に感じられる場所をつくるってのは非常に気持ちいいアプローチですよね。
藤本:すごいめちゃくちゃ分かってくださってる感じがします。うれしい。
——お祭りって旧来そういうものですよね。日常を一度切断して、その場所にいつもと違う時空をつくることで、普段の関係性をリセットできたり、どんな人も一緒にはしゃぐことができたり。祭りの力を活かしながらも、関西的なノリが大切にされていて、めちゃくちゃ参加してみたくなりました。
藤本:結局、ハレの日だけじゃ深い変化は生まれなくて、ケとしての日常がどう変わっていくのかが大事なんです。しかも、これは行政の啓発事業なんですよ。だから障害のある人が社会参加をする場をつくるってことと、障害のある人たちへの理解を深めることを事業目的にしてるんですけど、イベント一発やって障害者のことがわかるなんてありえないじゃないですか。一応イベントをつくるというお題目はあるにせよ、半年ぐらいかけて、月1〜2回ぐらい集まりながら、たまには遊びつつ関係性をつくっていく、その半年のほうがむしろ価値があると僕は思ってるんです。未来から逆算するんじゃなくって、今この瞬間しかない中で、どうプロセスを充実させていくのかを考えるほうが面白い。先にビジョンを描くのは大事やと思う一方で、そうじゃない世界をどうつくるのかっていうのが僕のテーマなんです。今あるものが全てではないし、それに合わない人が実は結構いたりします。そこで生きづらさを感じてる人たちがいるのであれば、現状に対するカウンターやオルタナティブをつくっていく必要あるんだろうなと。
——カウンターというよりは、オルタナティブ的に感じますね。主流の価値観を壊しにいくというより、傍流をつくっているような。
藤本:アウトプットはオルタナティブなんですよ。でも、ハートはむちゃくちゃカウンターなんです。
——なるほど。
藤本:怒りというか、「なんでそんなことになってんねん」「めちゃくちゃ苦しんでるやつおるやん、俺もそうやし」みたいな気持ちがあります。でも今は激しいアウトプットをする時代ではないような気がしてるんです。障害者運動や労働運動は、既存の権力構造を崩して権利を獲得していくプロセスだったと思うんですけど、今みんなを説得するには対立構造をつくるよりも、「こっちのほうが面白いと思うねんけどどう?」みたいな感じがめっちゃ大事なのかなと。

——出発点は怒りにあるんですね。優しい取り組みをつくる人だったので、てっきり聖人君子みたいな人かと思ってました。(笑)
藤本:全然そんなことないです。怒りってのは第2次感情なんで、怒りの前にやっぱ悲しいとかつらいとかもどかしいって感情があるんです。僕の場合は過去の両親との関係が結構大きな問題として横たわっていて。母親が5歳の頃にいなくなったり、父親も15の頃に突如家から出ていったりと、家族という一番身近な人間関係をうまくつくれなかった、ある種の強い絶望があるんです。だから人間関係には苦手意識があったし、あまりいいイメージがなかったんです。でも成長していくなかで、人間に傷付けられることもあれば、救われることもあるんだと知りました。であれば、できるだけポジティブな影響があるような場や関係性を自分もつくりたいなと思ったんです。
そこから人に会ったり話を聞くのがめちゃくちゃ好きになりました。人の話を聞くと、みんな普通に生きてるように見えても、実はしんどいこともたくさん抱えているんです。しかも、本人というより周囲の環境に問題があるケースがけっこう多い。だから個人がどうというより、問題が起こってしまう状況や制度、仕組みに対しての怒りというか、もどかしさがあるんです。それが僕のモチベーションになっています。
——コミニケーションをとおして知る誰かの辛さや苦しみが活動の原点になっていたりもするんですね。
藤本:本音のコミュニケーションからプロジェクトつくるのがめっちゃ好きなんです。同世代の友人でアクティブな車いすユーザーがいるんですが、彼は新型コロナの影響で講演活動ができなくなってしまいました。そこで人生で初めてのバイトを探してみたらしいんですが、障害者ができるバイトってほぼ皆無らしいんですよ。一応、企業には一定数の障害者雇用枠があるんですが、そんなに充実感のある仕事がない。そういう時の残念な気持ちをもとに、将来こうなったらいいよねというイメージをプロジェクトにしていくのが僕にとっての遊びなんですよ。
——仲間とのプロジェクトづくりが遊びだと。
藤本:現代の遊びって、お金を払って遊ばせてもらってる状態が多いじゃないですか。これ消費してるだけちゃうの?みたいな。自分たちでルールを決めて主体的に取り組むクリエイティブな遊びがいいんです。
——そう考えると、藤本さんの書籍『場づくりという冒険』は、上手に遊んでいる人や普通とは異なる世界観を表現している人を紹介する本だったように思います。
藤本:どれも社会的な要請のもとやっていない取り組みですからね。勝手に何かをやっている人が僕は大好きなんです。かつ、オルタナティブをつくろうとしてる人たち。書籍に出てくる活動でいうと、「前田文化」とか「はっぴーの家」はかなりお薦めです。
——藤本さんも書籍の中で、「今、評価されてることに対してはあんまり価値を感じない」ということをおっしゃっていました。
藤本:僕、めっちゃいいこと言ってますね。(笑)
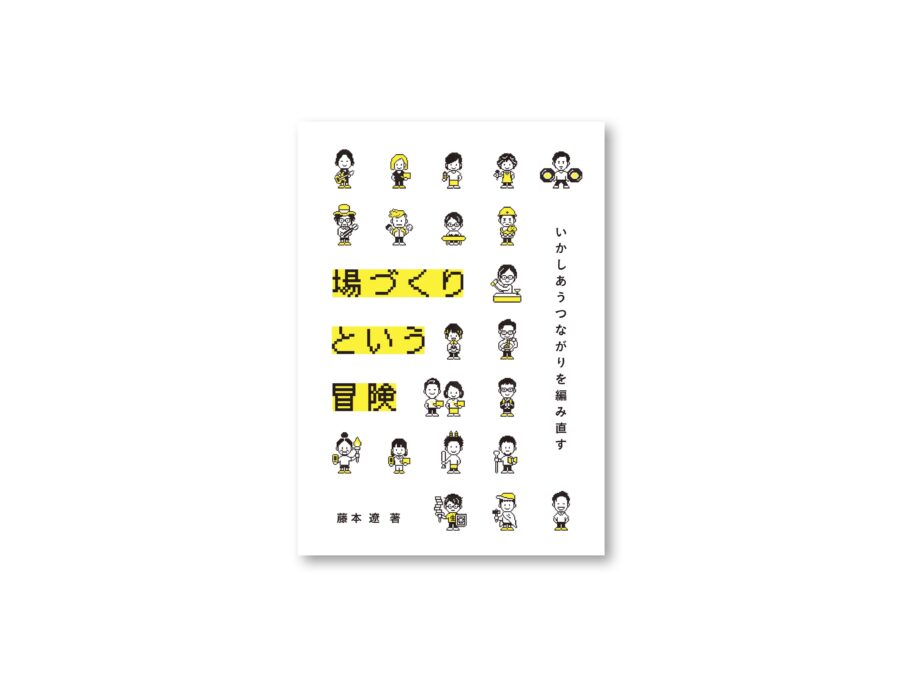
他者と共にいるために、場の概念を捉えなす
——「ここにある」という藤本さんのキーワードに関してお聞きしてみたかったことがあるんです。というのも、ここにあるためには逆説的にここではないものと接触することも非常に大事ではないかと感じているんです。人は自分が思っているほど自分自身について知りません。「ここにある」を全うするには、周囲の環境や他者をとおして、知らなかった自分を理解していくプロセスが必要な気がするんです。藤本さんが具体的な取り組みの中で人々が「ここにある」ことをどのように支援されているのかお伺いしてみたいです。ここまでのお話を聞いていると、1人よりもみんなで、という点は大切にされているように感じたのですが。
藤本:相手と認めあうために「共にいる」というのはすごく大事な気がします。あとは、評価がつきまとう時代だからこそ、評価をしない/されない場づくりは心がけていますね。ミーツ・ザ・福祉の会議でも、障害のある人が参加するので、目が見えない人や耳が聞こえない人が同時に参加した時にどうなるかを考えていろんなツールを使ったり、ルールを制定したりしています。いろんな人たちが居心地良く共にいる場は日々模索してるような気がしますね。
——本当の意味で相手と認め合うには、時間がかかりますよね。
藤本:長いスパンで考える必要がありますね。ビジネスやったら、ある程度の期間で売り上げを立てないといけないんですけど、地域づくりはすごく時間がかかります。変化が生まれるまでに7~8年ぐらいはかかると思いますね。そのためには共にい続けないといけないので、能力に関係なくお互いが一緒に楽しく生きていける場を考えていかないといけません。

——「場」という言葉は空間的なものをイメージしがちですが、時間的な方向からも捉えることができそうです。
藤本:よく想定される場っていうのは、現代を生きてる人の横のつながりなんですよ。最近「コミュニティ」という言葉がすごく注目されてますけど、コミュニティっていうのは共通性を持った集団なんですよね。ガンダム好きの集まりとか、同じ地域に住んでる人の集まりとか、何か共通することがあって集まっている。そこには常に排他性が潜んでいるので、異なるものとどう関わるのかという視点で場を捉えないといけないんです。だから違いをどのようにつないでいくのかを意識をしながら場をつくっています。
あと、想定している範囲が人間までなんですよね。もっと広く考えてみると、植物とか動物とかいろんなものがあるはず。横の広がりを人間だけにとどめずに場を考えていくことはすごく大事だと思います。
加えて縦のつながりも重要です。ビジネスの話でいうと、四半期後の売り上げがどうなのか、みたいなタイムスパンの短い思考になってしまっています。インディアンは7世代後のことを考えて意思決定をしていたという話があるじゃないですか。それは200年〜300年後のことを考えて意思決定をするということで、今の僕らの感覚からすると遠すぎるんだけど、そういう縦のつながりが完璧に寸断されてしまうと、思考がキュッと押し込められて孤独になっていく気がするんですよ。
——場という言葉を捉えなおすことで、その可能性を拡げられると。
藤本:そうなんです。だから僕は横の広がりと縦のつながりをつくっていくという意識で場を捉えています。
——コミュニティや場づくりという言葉はいろんな場面で使われていますが、空間的にも時間的にも拡がりがあると捉えることで、私たちが共にいるための足場である「ここ」は拡張することができる。ここを離れて思考することで、この場所の豊かさに気づけるのだとすると、場を再定義することの重要性を感じます。
ワークショップよりも、まずは一緒に飯を食え
——場をつくる上で、人とのコミュニケーションには力点を置かれてるかと思うのですが、やはりプロジェクトを進める過程で話し合いをする機会は多いでしょうか。
藤本:そうですね。話し合いをメインにした取り組みはあまりないですが、ファシリテーターとして場の進行を担当する仕事はあったりします。でも僕は話し合いをしたいというよりもオルタナティブな価値をつくりたい人なので、必要な時には話し合いを取り入れるいう感じかな。
——話し合いが必要なのはどういった場面なんでしょう。
藤本:見えないものって信じられなかったり、よく分かんないじゃないですか。感度の高い人は、やることから結果が想像できるけれど、一般的には「それってどんな意味があんの?」とか「やって何になるの?」って反応されることも多々あると思うんです。
だから話し合いが通用するには、一定の前提を共有してることが必要なんです。世界観が全く異なった人たちとの話し合いってめちゃくちゃむずかしいし、僕はそこで話し合う必要ってあるのかしらと思っていて。むしろ、「僕らが言ってることはこういうことだったんですよ」っていうふうに事例を見せるほうが分かり良いじゃないですか。行政も、前例がないことや、よく理解できないことに予算はつけてくれないけど、「尼崎ではこんなふうにやってこんな価値が生まれてますよ」と伝えられると、「じゃあウチでもやってみてほしい」という話になったりする。前提を共有しているかどうかで、話し合いの円滑さや面白さは変わってくるはずです。

——なるほど。共通の価値観をシェアできる人たちだからこそ、話し合いが機能してチームが生まれていくわけですね。
藤本:そうですね。僕はプロデューサー気質なので、プロジェクトの前提部分を組んだり、仲間に声をかけていく立ち上げ段階の動きが多いんです。毎日無駄なやりとりをいろんな人たちとしてるので、「次はこんなことをやろうと思ってんねんけど」って声を掛けやすい人たちが周りにたくさんいる。よい話し合いをするための事前準備ってめちゃくちゃたくさんあるはずなんですよ。よくわからない人が集まってその場をよい話し合いにしろ、って言われると僕のスキルじゃできないかもしれないけれど、事前の関係性づくりや人々が関わる意味づけをしていく前提部分のプロセス設計が僕のほうでできるのであれば、よい話し合いの場をつくれると思います。
——よい話し合いは、事前の準備段階にかかっていると。
藤本:ワークショップするよりもまずは一緒にご飯を食えと思いますね。その方がよっぽど人間性が分かるし、一見無駄な話をするほうが大事だと思いますよ。
——プロジェクトをつくっていく過程で、みんなでご飯を食べる機会を意識的に組み込まれたりするんでしょうか。
藤本:プロジェクトをうまくいかせるためにご飯を食べに行くみたいな打算的な場はゼロじゃないかもしれないけど、ほとんどない。だってそれ、面白くないじゃないですか。それは「仕事」やから。仕事的な時間を極力生活の中から排除するっていうのが大切というか。
——「行きたいから行く」じゃないといけない。
藤本:そうです。でもまあ、いろんなこと考えちゃいますよね、行っといたほうが得なんじゃないかとか、仕事的には行っとかなあかんよなとか。
——形式的な場をつくるよりも、みんなが心から遊べるような関係を紡ぐのが先決だということですね。

藤本:できるだけ遊びで来てほしいんですよね。仕事を発注してくださる人も、仕事かもしれんけど遊びの心を忘れないでほしいんです。例えば、行政の仕事などは、担当課の方が会議の場を見に来られたりするんですよ。そういう時、大体は会場の後ろに座られるんですが、僕は絶対に「みんなと一緒のテーブルに着いてしゃべってほしい」と言うんです。そこで関係性が生まれたら、その後どっちにもいい効果があるんですよ。
——参加者のみなさんが興味や好奇心をもって主体的に関わってくれる場が理想ですね。
藤本:ちなみにゲストを呼んでトークイベントをする時は、基本的にすでに関係性のある人に声をかけます。関係性がない人であれば、事前に会う機会を必ずつくるようにしています。そもそも、場をうまく回したいというよりも友達になりたいんですよ。であれば、事前にいろいろ話を聞いて、思いを交わして当日向かったほうが、相手も僕も安心してしゃべれるので。
——言葉というより、思いを交わすと。
藤本:話が上滑りする時ってあるじゃないですか。自分のイメージを気にして本音でしゃべってなかったり、ポジショントークになってしまっていたり。僕もいろいろな失敗経験があるんですが、そういう時は思いをちゃんと受け止め切れてなかったり、掘り下げようとしたりしてなかったんですよ。ちょっとこの考え方受け入れられへんわとか、好きじゃないわって思っても、相手の人生を想像して、その考え方って普通だよねと捉えられたら、相手に対して愛が生まれてくるというか、完全な他者に思えなくなるんです。俺もその人生を歩んだら絶対そうなるわ、みたいな。相手が自分のようであり、自分が相手のようでもあるという感覚を対話の場でつくれると、しゃべれてよかったなという気持ちになりますね。
話し合いの外側にあるコミュニケーション
——自分と他者が溶け合うような経験は、それ以後の対話にも大きな影響を与えてくれそうです。そういう場の中で、強く記憶に残っているものはありますか。
藤本:ある、ある。めちゃめちゃ失敗事例なんですけど、駆け出しの頃に淡路島のある町からファシリテーターとしてお呼びが掛かったんです。その時は、海の上に新しい風車をつくって発電して、行政や漁協でお金を生み出していこうというプロジェクトでした。ただ、景観や騒音、電磁波の問題を考慮すると、そんな計画は許せないという住民の方もいて、地域と行政が揉めているような状態だったんです。いろいろ準備をして向かったんですけど、始まる前からすごい炎上していて。(笑)僕の持っているマイクも奪われるみたいな。
——それは大変ですね。(笑)
藤本:事前に考えていた計画どおりに進めるのは無理だと判断して、「いま心に溜まっている不安や怖さを全て正直に話してみましょう」と伝えました。そうすると、すごく場が変わったんですよ。最初は「おまえ、どっから来とんねん」と怒っていた人も、最終的に「お互い大変だよね」みたいな結論に行き着いたり。大人って、本当の感情を出さずにロジックで戦おうとするんですよね。でも本音はもっと本能的なものなので、それを共有していかないと上滑りするんです。
——お互いの本音をわかりあうプロセスを抜きに、よい話し合いは実現しないということですね。
その経験を経て、企画を進める時は本音を共有できる人と一緒に進めることにしてるんです。例えばカリー寺であれば、中平さんというお坊さんと企画をしています。考え方が違ったりする部分もあるんですが、本音をしゃべれる関係があるので、言葉がぶつかったりすれ違っても全く問題なくて。それはすごいヘルシーな関係性だなと思ったりします。

——まずは相手を尊重することが大切なんでしょうね。他者と自分の違いを理解しあった上で、思いを共有していく。
藤本:話し合いでできることって、めちゃくちゃ知れてるじゃないですか。全てを言語で表現しようとする僕らは、たくさん落とし物をしてるはずなんですよ。言語を交わさない時間や、言語以外のコミュニケーションを考えることが話し合いにとって大事な気がします。でも忙しくなると、会議以外の時間がとれなくなるんですよね。無駄な遊びの時間を一緒に過ごしていたからこそ円滑に回っていた会議が、会議しかしないことによって、滞ったり面白くなくなったりするんです。
——なるほど。
藤本:忙しくなり過ぎると全然おもんなくなるんですよ。だから僕らにはもっと暇が必要。暇であればあるほど、無駄な時間が取れるんです。
——確かに。最近は新型コロナウイルスの影響もあって、これまで以上に言語でのコミュニケーションに偏ってしまっている印象です。
藤本:そうですね。ただ一緒にいるだけで入ってくる情報ってたくさんあるので。話し合いの外側を見直さないといけない。
——今日は話し合いや言語に欠けているものについて考えなおすことができました。これからはDo(する)ではないBe(ある)のコミュニケーションの可能性についても探究していきたいと思います。
藤本:「よい話し合いとはなにか」の前提ばかりをしゃべってしまいましたが、それでよかったような気がします。とても面白かったです。
——貴重な問いをいただきました。今日はどうもありがとうございました。